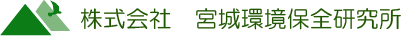風薫る5月は足早に過ぎ去り、月めくりのカレンダーは6月を示す。この1枚で今年も半分は終わるのかと思うと、改めて月日の流れの速さを感じる。
前回は、日本気象協会の発表による「季節のことば36選」を紹介した。現行の太陽暦に調和する季節感のある言葉を各月ごとに3題ずつを選んだもので、6月の言葉は「あじさい」「梅雨」「蛍舞う」であった。アジサイについては、既に本誌(No.21)で紹介してあるので、今回は同じ時期に開花するキリを取り上げてみた。
桐の字がわが国の古典に初めて表われたのは万葉集。天平元年(729年)、太宰府長官大伴旅人が、藤原房前に宛てた書簡(巻五)に、梧桐で作った日本琴を贈る旨の記述がある。この梧桐とは、本シリーズ(No.58)でも記述してあるように別種のアオギリのことだが、この木で琴は作れない。従って、旅人が贈った琴は、本物の桐で作ったものとみて間違いはない。
明らかに桐と出ているのは枕草子。清少納言は、気品のある木の代表に桐を挙げ、「紫に咲きたるはなほをかしき」とその風情を称えている。また、源氏物語の冒頭を飾る「桐壷」の巻は、高貴な花として宮廷に植えてある桐に由来するといわれる。

このように桐は古典に再三述べられているが、なぜか桐の花に関する歌は詠まれていない。鎌倉時代の勅選・新古今集に秋の題として、桐の歌が数首入っているが、ここでも専ら桐の葉を対象としており、花については詠まれていない。
和歌として桐の花が登場するのは江戸時代の末期のこと。文化8年(1811年)刊の歌集「六帖詠草」に次の歌が載る。
作者は小沢蘆庵。桐の花散る叙景を巧みにうたっている。近世に入り、桐材の需要が高まり、キリの植林は北海道南部以南の日本各地に広まる。その栽培の過程で見られる美しい紫の花と甘い香りが多くの人に愛され、盛んに詠まれるようになる。
特にこの二人は、桐の花に大分興味があったようで、龍之介は「芥川龍之介歌集」に、また白秋は「桐の花」に、多数の桐の歌を収めている。なお、2首目の「かはたれ」は、「彼は誰れ」のことで、人の顔の見分けもつかない、うす暗い夕刻どきを表す。
キリ(Paulownia tomentosa)は、古くから栽培されるゴマノハグサ科の落葉高木。十分に生育させれば樹高15m、胸高直径70cmに達する。しかし、多くの場合、生育の途中で伐採されてしまう。キリは成長が早く、20年生くらいで利用できるからである。
葉は通常、対生につくが、まれに3葉輪生のものもある。葉身は広卵形で、日本産樹木のなかでは最大級。種小名が多毛を意味する(tomentosa)とあるように、葉面に綿毛が密生する。
花期は初夏。葉に先立って枝先に大型の円錐花序を作り、多数の花を下向きに咲かせる。花弁は紫色の筒状花で先端は5裂する。花後、長さ5cmほどの蒴果となり、内部に翼のある種子が多数入る。

キリは、中国からの伝来とする説が有力。しかし韓国やわが国の岩手県、大分県の山中に野生状態の古木や伐根があり、原産地ははっきりしない。岩手県では桐の花を県花に指定している。
貝原益軒が、編集した大和本草(1708年)に、「この木切れば早く長ず、故にキリといふ」とあるように、キリの名は切りに由来する。実際に種子から発芽したままの状態で伸ばしても成長は良くない。発芽した翌年、根元近くで切り取ると、新梢は一気に伸びる。これを台切りと称し、枝下高の長い良質の材を生産するには、必ずこの作業を行う。
キリ材は比重が0.28~0.30で、日本産木材のなかでも最も軽い。材はくすんだ白色を帯び、燃えにくく、狂いも少ない。このため古くから箪笥、長持、琴、下駄などの絶好な材料として賞用されてきた。
ひところ、農村などでは女の子が生まれると、キリの苗を植える風習があった。その娘の嫁入り道具にする箪笥を作るためである。
古川柳に次の句がある。
かつての女性の初婚は18歳前後。キリもこの樹齢になれば十分に利用できたのである。ついでにもう1句。
人生の運と同じように、キリも琴になって床の間に飾られるものもあれば、下駄になって履きつぶされ、捨てられるものもあるという格言のような句。
俳句では、草創期の江戸時代初期以来、「桐の花」を初夏の季語として、多数の句が詠まれている。まずは、元禄時代に作られた蕉門の句を紹介する。
芭蕉の高弟其角は、神殿と、そばに並び立つ桐の花を同格に扱っている。これは桐の花を高貴とする平安時代の思想が当時も潜在していたからと思われる。桐の花を自由に意識して句が詠まれるようになるのは明治期に入ってからである。
文豪による自由律の句。荷風の句の御家人とは元旗本に仕えていて、職を失った下級武士のこと。
近世俳壇の巨匠たちがうたう自由奔放な句である。
夫唱婦随でうたう桐の花の句。